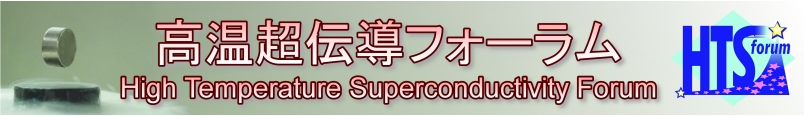設立趣意
銅酸化物高温超伝導体が発見されて26年になろうとしていますが、
残念ながらいまだそのメカニズム解明には至っていません。
あまりに長い時間を費やしてしまったため、また研究手段があまりに高度化したため、
研究者人口が著しく減少し、日本国内では銅酸化物超伝導体研究者は
ほとんど「絶滅危惧種」のようになっています。(例えば、今春の日本物理学会領域8において、
銅酸化物のセッション数は領域全体の1割弱でした。)
一方、世界に目を転じると、銅酸化物高温超伝導の研究は、ヨーロッパやアメリカを
中心にまだまだ活発に行われております。
例えば、今夏ワシントンで開催された国際会議Materials and Mechanisms of Superconductivity (M2S)では、
月曜から金曜までExcursionもなくぎっしり詰まったプログラムのほぼ全時間帯に
銅酸化物のセッションがありました。
全体として大体、銅酸化物3割、鉄系超伝導体4割、残り3割をトポロジカル絶縁体、
有機超伝導、重い電子系などその他の超伝導が占めていたと思います。
会議には多くの日本人が参加し、日本人の招待講演者も大勢いましたが、
銅酸化物セッションで講演した日本人はたった一人だけ、という寂しさです。
世界の中での地位低下は目を覆うばかり、と言わざるをえません。
研究停滞の影響は、試料作りにも及び、上記M2Sにおける銅酸化物関係の発表で、
日本から試料提供された研究はほとんどありませんでした。かつて世界中に
日本製の結晶が出回っていたのがウソのようです。日本は確かに世界の銅酸化物研究を
牽引した国の一つでした。それにも関わらず、メカニズム研究が煮詰まってきたこの時期に、
ほとんどの研究者が撤退しているという現状は、残念でなりません。
以上のような問題意識・危機意識が、本フォーラム設立の背景です。
中国や韓国といった後発国では、銅酸化物のような“歴史が長く困難な課題”には手をつけない、
と当事者達から聞きました。それに対し、欧米諸国の研究機関が、忍耐強く薄皮を
一つ一つ剥ぐように銅酸化物研究を進め、ブレークスルーを成し遂げている姿には、
研究の底力・実力の大きさを見せつけられる思いがします。
銅酸化物研究こそ、先進国の特権であるように見えます。
日本には、J-PARC, SPring-8, スーパーコンピュータ京、超強磁場施設など、
世界に誇る実験施設が数多くあります。光電子分光やトンネル分光などの装置も
世界トップレベルです。世界に発信できる成果を挙げられる研究基盤は、
十分整っているといってよいでしょう。
また、幸いにして日本でも鉄系超伝導の研究は活発に行われており、超伝導研究における
日本の力を示しています。この力をバネにして、銅酸化物超伝導の研究に新しい息吹を吹き込み、
さらには新超伝導物質の発見、新超伝導機構の研究につなげていくことが強く望まれます。
本研究会の目的は、「銅酸化物を含む新しい超伝導機構の物質研究を継続・
活性化するための会合を行い、次世代の人材を育成すること」です。
対象物質は銅・鉄化合物に限定せず、広い視点からの議論を目指します。
当面の会の活動としては、以下の2つです。
1)物理学会におけるシンポジウムの企画提案(年1回)。
2)機構解明関係や物質探索関係などテーマを絞った研究会を、年2回開催。
(東北或は関東で1回、関西で1回の開催を目指す。)
発起人(50音順)
永崎 洋 (産業技術総合研究所)
小形 正男 (東京大学)
黒木 和彦 (大阪大学)
笹川 崇男 (東京工業大学)
田島 節子 (大阪大学)
鄭 国慶 (岡山大学)
遠山 貴巳 (東京理科大学)
花栗 哲郎 (理化学研究所)
藤田 全基 (東北大学)
椋田 秀和 (大阪大学)
吉田 鉄平 (京都大学)
入会申込み
入会希望者は、「会則」をご確認の上で、
氏名・所属・メールアドレスを
enrollment@htsf.jp(※大文字@を小文字@に変更して下さい)
にご連絡ください。
賛助会員の募集
上に記した本会の目的ならびに活動内容にぜひともご賛同いただき、
ご加入下さいますよう、心よりお願い申し上げます。
なお、賛助会員には団体でも個人でもご加入できます。
ご加入の申込みは「賛助会員のご案内」をご確認の上で、
enrollment@htsf.jp(※大文字@を小文字@に変更して下さい)
にご連絡ください。
|